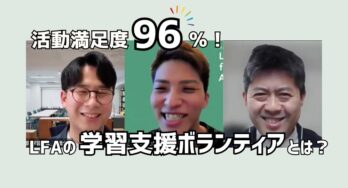活動満足度96%!Learning for All の学習支援ボランティアとは? 〜名古屋市立大学 松村准教授対談インタビュー 前編〜
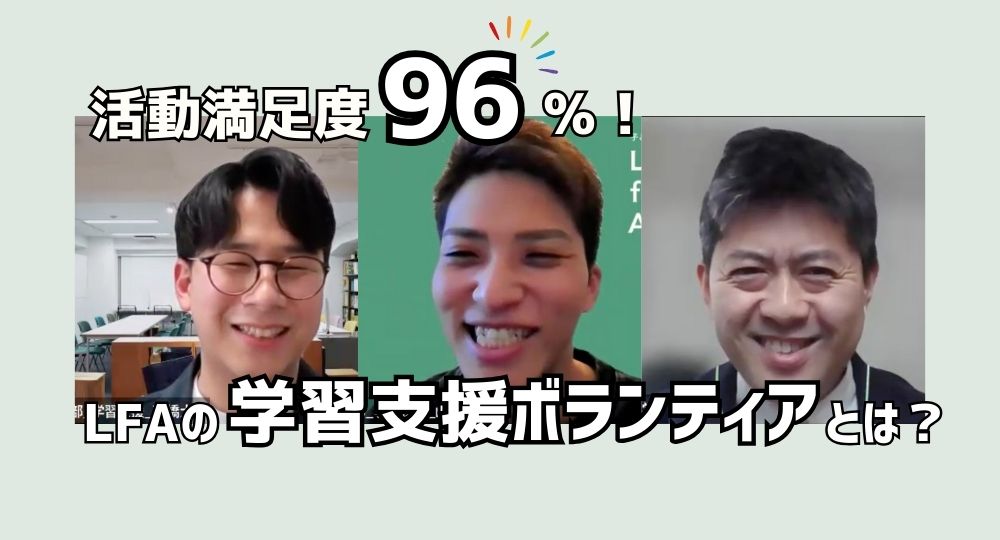
みなさん、こんにちは!
ボランティア採用の勝又です。
今回は、少し特別な記事となっております!
学習支援領域の研究をされている名古屋市立大学の松村智史(まつむら さとし)准教授をお招きし、Learning for All の学習支援ボランティアについて対談インタビューをさせていただきました!
松村先生は、2023年よりLearning for All の学習支援について調査をされています。
この度の調査の中で、Learning for All の学習支援プログラムにボランティアとして参加された学生の皆さんが、非常に高い満足度を感じてくださっていることがわかりました。
Learning for All 学習支援拠点長の髙橋大咲(たかはし だいさく)さんにもご参加いただき、実際の拠点の様子についても詳しくお話しいただいております。
LFAのボランティアを詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください!
まずは自己紹介!
山下:
学生人事チームの山下と申します。
ボランティアをしてくれる学生さんの採用や、採用後の研修を担当しています。
以前は、髙橋さんと同様に学習支援の拠点長として現場で子どもと関わっていました。
本日は、司会を務めさせていただきます!
髙橋:
学習支援プログラムで拠点長をしている髙橋と申します。
約1年半前にLearning for All に入職し、現在は、葛飾区にある拠点の運営をしています。
本日は、よろしくお願いします!
松村准教授:
名古屋市立大学で教員をしております松村と申します。
普段は学習支援に関する研究をしており、研究柄これまで何百人とインタビューをしてきました。
自分自身がインタビューを受ける側になるのは初めてで、少し緊張しています。
今日は、お話しできることをとても楽しみにしておりました。
「Learning for All のボランティア活動には何が起きているのだろう」と思ったことがきっかけ
山下:
まずは、松村先生がLearning for All のボランティアの調査を開始された背景やきっかけをお伺いしても良いでしょうか。
松村准教授:
学習支援に関する研究をする中で、様々な団体さんや学生さんからお話を聞く機会があるのですが、Learning for All さんのボランティア活動に対する評価が非常に高かったんです。
特に、参加経験のある学生さんが「また参加したい」「友人にも勧めたい」とお話しされるのをよく耳にしていました。
一方で、学習支援業界全体を見ると必ずしも支援をする人が集まっている状態ではなかったり、活動を長く続けることが困難だったりするんです。
このような人の出入りが激しい業界の中で、Learning for Allさんでは非常に多くの学生さんが参加し、継続し、さらに生き生きとやりがいを持って活動をされている。「これは一体何が起きているんだろう」と関心を持ち、調査を依頼させていただいたことがスタートでした。
山下:
直接ご連絡をいただく前から、わたしたちのことを知ってくださっていたんですね。
松村准教授:
そうですね。
学習支援業界の関係者の中でも、業界を引っ張っていくような、素晴らしい取り組みをされているとお聞きしていました。
山下:
お褒めの言葉をいただき大変恐縮ですが、同時にとても自信に繋がります!
ここからは、さっそくいくつかの調査結果をピックアップしながらお話を聞かせていただきます。
ボランティア自身に学びや気づきがあることが満足度に繋がっている
山下:
まずは、活動への満足度約96%という結果についてお話しできればと思います。
松村先生お聞きしたいのですが、この数値は一般的に高いのでしょうか。
松村准教授:
極めて高い数値と言っていいと思います。
これまで様々な学習支援活動を調査してきましたが、ここまで高い数値は見たことがありません。
学習支援という活動はやりがいもある一方で、決して楽な活動ではないです。
自分が楽しみたいというだけではなく、一人ひとりの子どもに向き合うので、我慢強さや責任感も必要。それにも関わらずこの数値が出ることに驚きました。
満足度の背景としては、支援者側であるボランティアやインターン自身に大きな学びや気づきがある、仲間づくりや関係性が広がった、自分自身のロールモデルとなるような人が組織の中にいた、という声が多かったです。
山下:
先生から見ても高い数値だったんですね!
髙橋さんにお伺いしたいのですが、拠点で行っている工夫のなかで「活動の満足度の高さ」に繋がっていそうなことはありますか。
髙橋:
大きくは3つあるかなと思っています。
まずは、担当制で子どもに向き合っている点です。
ボランティアの方には、1~2人の子どもを専属で担当して指導をしていただいているので、1人の子どものことを深く考えられる環境だと思っています。
あとは、インターンとボランティアでバディを組むメンター制度というものを設けています。
ボランティアの方が抱える不安・悩みを解決しながら指導できる環境を作ることを目的として、「今週の指導は何をしようか」「どんなことを目標におこうか」ということを相談する時間があります。
最後に、毎週の指導後に振り返りの時間を設けています。
活動の中で、大変なこと・苦労することはもちろんありますが、ボランティアの方1人にお任せするのではなく、ボランティア・インターン、そして拠点職員といったチームで困りごとを共有することを大切にしています。
こういった環境で活動いただくことによって、子どもの支援はもちろんのことボランティアの方の成長に繋がる機会になっているのではないかと思います。
山下:
改めて、縦にも横にもつながりがあることは自分たちの強みなのかな、と感じました。
振り返りの時間があるとお話しいただきましたが、具体的にはどういった時間を過ごしているのでしょうか。
髙橋:
その日の指導について、事前に考えた指導案を元に振り返る時間です。
指導の場面で、子どもはどう感じたのか、何を思っていたのか、ということを考えたり、上手くいった要因・上手くいかなかった要因を振り返ったりしながら、次の指導をより良くするために実施しています。
山下:
上手くいかなった要因だけではなく、上手くいった要因も振り返るというのは、Learning for All の特徴の1つですよね。それによって再現性を持たせることができると僕も現場にいたときに感じていました。
いかがでしたでしょうか。
今回は、名古屋市立大学の松村先生をお招きし、Learning for All の学習支援ボランティアについて対談インタビューをさせていただきました。
前半では、松村先生がわたしたちLearning for All の学習支援について研究されたきっかけや、活動満足度に関する調査結果についてお伺いしました。
後半は、3月28日(金)にアップ予定ですので楽しみにお待ちください!
「LFAでボランティアをするか迷っている」という方、わたしたちボランティア採用チームは皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
エントリーはこちらから!