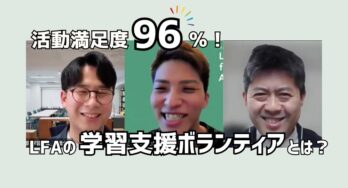活動満足度96%!Learning for All の学習支援ボランティアとは? 〜名古屋市立大学 松村准教授対談インタビュー 後編〜
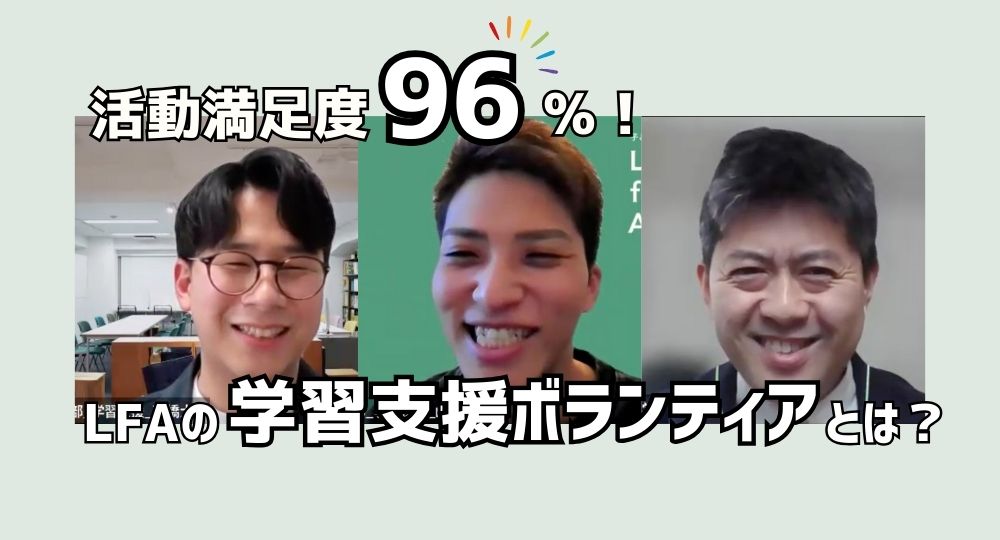
みなさん、こんにちは!
ボランティア採用の勝又です。
今回も、前回に引き続き名古屋市立大学の松村准教授をお招きし、Learning for All の学習支援ボランティアについての対談インタビューをお送りします。
後編では、学習支援ボランティアに参加した学生にどんな変化があったのか、また学生たちに有意義な時間を過ごしていただくために、Learning for All ではどのような取り組みをしているのか、についてお話しいただきました。
学習支援拠点長の髙橋さんにもご参加いただき、実際の拠点の様子についても詳しくお話しいただいております。
LFAのボランティアを詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください!
振り返りや研修を通して、少しずつ価値観が変化していくボランティア
山下:
他にも、「自分の将来をより考えるようになった」、「教育への関心が高まった」などの項目でも約90%の方が当てはまると回答してくださっています。
松村先生、この辺りは具体的にはどのような声が多かったのでしょうか。
松村准教授:
Learning for All さんで活動をする中で、たくさんの出会いや気づきを通して自分自身の視野や関心が広がったというお声が多いです。
将来のキャリアに直結しなくても、こういった困りを抱えた子どもが存在すると知れたことが自分の財産になり、子どもを取り巻いている社会問題を自分自身の問題としてずっと考えていきたい、などと話してくださる学生さんもいらっしゃいました。
山下:
ボランティアの学生さん自身も、活動のなかで変化している実感があるのですね。
髙橋さんは、一緒に活動するなかで学生の変化を感じる瞬間はありますか。
髙橋:
学生自身の価値観の変化を感じる場面が多いですね。
わたしたちの活動は、自分自身の価値観を深掘りする機会が多く、かつ周りのメンバーの価値観に触れる機会も多いと考えています。
例えば、活動時間を通して自分が感じたことを振り返る際に、「なぜ自分はそう感じるのか」「そう感じる背景にはどんな原体験があるのか」など自分に向き合う時間が多く設けられているんです。
その上で、自分の価値観を一旦横に置き、周りのメンバーはどんな価値観を持っているのかといった意見交換をする時間があります。
自分自身の価値観と相対する時間が多いゆえ、そういった変化を目にすることは多いと思います。
山下:
Learning for All は学生たちが参加する学習支援プログラム期間の中で、計4日間の研修を実施していますよね。
学習支援拠点では、どのような研修をされているのでしょうか。
髙橋:
子どもの支援技法や指導方法はもちろんですが、子どもの背景にある社会課題について学ぶ機会も用意しています。
例えば今年度は、子どもの人権についての研修を実施しました。
実際に子どもたちと過ごす中で、子どもの権利が阻害されていると感じる場面があります。
Learning for All は、今後社会課題に関わっていく人材を育成することも活動指針として掲げているため、学生の皆さんにはこうした子どもの権利についてもアンテナを張っていただきたい、という思いで研修を実施しました。
山下:
ありがとうございます。
学習支援職員の思いとして、このボランティア活動を経て、社会課題を解決できる人に成長していってほしい、そこに自分たちが伴走していきたい、という思いの表れだと感じました。
多様な価値観を尊重し合う文化だからこそ、仲間意識が芽生える
山下:
最後に、「社会課題への関心を共有できる仲間に出会えた」という項目も約90%の方が当てはまると答えてくださっています。
松村先生、こちらの具体的な学生の声を教えていただけますでしょうか。
松村准教授:
こちらの項目は、学生へのインタビューをする中でも非常に濃い語りがあったと思っています。
まずは、研修や振り返りがとても充実していて、かつそういった時間を仲間と共に取り組むということを通じて仲間意識が芽生えてくるという声が多かったです。
また、髙橋さんがお話しされていたバディ制度・メンター制度のおかげで「すごく相談がしやすい」とお話されていました。
日々のコミュニケーションの中で、自分自身を内省したり、成長を確認したり、他者からアドバイスをもらえる機会をプラスに感じている学生さんが多いように感じます。
また、これも特筆すべき点かと思いますが、団体内でもお互いを尊重し合う文化がとても浸透しているなと感じました。
多くの団体や活動では、リーダーが“これ”と言ったらその方向だけをみんなで目指しがちだと思っているんです。
しかし、Learning for All さんにはお互いの考えを交換し合い、尊重し合う文化があります。
人とは違うことを言ったとしても、それを責められずに「あなたはそういう考えなんだね」と受け入れてもらえる、そう言った心理的安全性があるということは多くの学生が話してくれました。
わたしが研究してきた中で、学習支援団体からそういう声が聞こえたことはあまり無かったので、すごく印象的でしたし、Learning for All さんの強みだと感じました。
山下:
拠点の職員も、子どもたちを中心に置きながら、ボランティアの学生さんにとっての最善の利益を大切にしています。だからこそ、ボランティア間で価値観の違いがあったときには、ディベートではなく対話をしていこう、という文化が根付いていると思います。
松村准教授:
そうですね。
本当に、Learning for Allさんならではの経験・気づきが得られたと多くの方が語っていました。
お互いがありのままの自分を尊重し、子どもへの支援という共通のミッションを目指していく中で、こういった仲間同士の繋がりが生まれていくのだと思います。
山下:
拠点では様々な学生さんが活動してくださっていると思いますが、どんな方が多いのでしょうか。
髙橋:
本当に多種多様な学生さんが参加してくださっています。
大学の授業をきっかけに社会課題を知って参加してくださる方、塾講師としてアルバイトをしていた方、中には自分自身がひとり親家庭で育ったり、経済的な困難を抱えていた方もいらっしゃいます。
また、子どもに勉強を教えたいという強い思いがある方もいれば、子どもには全く関わったことがないけれども支援をしたい、という思いの方もいます。
さまざまな思いを抱えた方が集まるからこそ、みんなで同じ方向を見る・みんなで支援していくという点は大切にしています。
山下:
具体的にはどのようなことでしょうか。
髙橋:
わたしの拠点では、プログラム期間が始まる前にわたしとインターンで、拠点全体の目標や大切にしたいことを話し合っています。
みんなで話し合いをすることで、子どもに何を届けたいかという目線を揃えることが目的です。
話した内容は拠点目標や文化として、研修の中でボランティアの学生にもお伝えをしています。
また、担当制で子どもの指導をするとお伝えしましたが、全員が全員の担当という意識も持ってもらうようにしています。
困ったときには周りに相談し、全員で子どもに支援を届けていくという考えを大切にしているので、自然と仲間意識が芽生えていくではないかと思います。
最後に
山下:
ぜひおふたりから、本日のお話を踏まえてご感想をいただければと思います。
松村准教授:
本日はありがとうございました。
Learning for All さんが学生さんにとって大きな学びや気づきの場となっていることは想定していたのですが、想像以上にその効果が大きいということと、それが偶発的に生まれるものではなく、仕組みとして根付いていることが本当に素晴らしいなと思いました。
インタビューした学生さんも、活動で得た学びが今後の人生の財産なっていくと、みなさん語っていました。
今後も、Learning for All さんには頑張ってほしいと思いますし、Learning for All を卒業されたみなさんが、社会にどういうインパクトを与えていくのかにも注目していきたいと思っています。
髙橋:
ボランティアやインターンをしてくださっている皆さんが、ここまで高い満足度を持ってくれていることは知らなかったので、職員としてとても嬉しかったです。
また、今後も研修や振り返りの機会がより良いものとなるようアップデートし続けていきたいと感じました!
山下:
おふたりのお話から、学生さんがさまざまな思いを抱えてこの活動に参加してくださっていることを改めて実感しました。
採用チームとしても、子ども、そして学生さんに一生ものの経験を届けられるように前進していきたいと思います。
いかがでしたでしょうか。
今回は、松村先生、そして学習支援拠点 拠点長の髙橋さんをお招きし、Learning for All の学習支援についてさまざまな視点から語っていただきました。
「LFAでボランティアをするか迷っている」という方、わたしたちボランティア採用チームは皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
子ども、仲間、そして新しい自分に出会ってみませんか?
エントリーはこちらから!